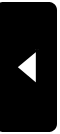2012年09月12日
泡杢(あわもく)
泡杢(あわもく)
比較的小さな円形の模様が散らばって現れるもので、水中に浮き上がってくる泡粒に似ていることからこう呼ばれる
玉杢は樹皮側に出現しやすく、樹心に近づくとなくなっていきます。この玉杢が消えていく境界にこの泡杢が出るのかもしれません。

比較的小さな円形の模様が散らばって現れるもので、水中に浮き上がってくる泡粒に似ていることからこう呼ばれる
玉杢は樹皮側に出現しやすく、樹心に近づくとなくなっていきます。この玉杢が消えていく境界にこの泡杢が出るのかもしれません。

2012年09月11日
虎斑(とらふ)
虎斑(とらふ)

ナラやオーク材などのブナ科に見られる斑紋で、柾目を横切るような帯状の杢目を「班」(ふ)といい、この班が大きく虎の毛のよう模様に見えるものを「虎班」という。虎斑は他の組織とは光沢が異なり、まさに虎の毛のように銀色に輝いているのが特徴
そのため、「銀杢」と呼ばれることもある。

広葉樹、特にナラには「虎斑」と呼ばれる細胞組織があります。木材用語では放射組織と呼ばれ、細胞全体の5~20%を占め、立ち木のときは養分貯蔵の役割を担っていた細胞です。
言葉の通り中心部分から年輪を横断するように放射状に広がっています。この放射組織は縦に伸びる繊維方向と直角に交わり、細胞の種類が異なるため、木材を柾目取りした場合必ず材面に模様が現れます。これが「虎斑」と呼ばれる模様です。

ナラやオーク材などのブナ科に見られる斑紋で、柾目を横切るような帯状の杢目を「班」(ふ)といい、この班が大きく虎の毛のよう模様に見えるものを「虎班」という。虎斑は他の組織とは光沢が異なり、まさに虎の毛のように銀色に輝いているのが特徴
そのため、「銀杢」と呼ばれることもある。

広葉樹、特にナラには「虎斑」と呼ばれる細胞組織があります。木材用語では放射組織と呼ばれ、細胞全体の5~20%を占め、立ち木のときは養分貯蔵の役割を担っていた細胞です。
言葉の通り中心部分から年輪を横断するように放射状に広がっています。この放射組織は縦に伸びる繊維方向と直角に交わり、細胞の種類が異なるため、木材を柾目取りした場合必ず材面に模様が現れます。これが「虎斑」と呼ばれる模様です。
2012年09月10日
2012年09月06日
縮杢(ちぢみもく)
私が思っていた以上に杢はたくさん有りました。
縮杢(ちぢみもく)
木目が波状に縮んでしわがよったように見える杢
縮緬杢(ちりめんもく)、波状杢(はじょうもく)とも言う
また、バイオリンなど弦楽器の甲板に重用されたことから「バイオリン杢」とも言う
栃(とち)、シカモア、カエデ類に現れる

縮杢(ちぢみもく)
木目が波状に縮んでしわがよったように見える杢
縮緬杢(ちりめんもく)、波状杢(はじょうもく)とも言う
また、バイオリンなど弦楽器の甲板に重用されたことから「バイオリン杢」とも言う
栃(とち)、シカモア、カエデ類に現れる

2012年09月05日
如鱗杢(じょりんもく) 筍杢(たけのこもく)
如鱗杢(じょりんもく)
魚のうろこのような木目

天井材やテーブル材などに高い価値を誇っています。
筍杢(たけのこもく)

樹木は元口より末口に向かって径が細くなるため、樹心に平行な板目の裁断面
には筍状に山形の杢が現れますスギ
やケヤキ
など、春材と夏材の差がはっきり
とした肌目のものが、分かりやすくて美しいとされます。
魚のうろこのような木目

天井材やテーブル材などに高い価値を誇っています。
筍杢(たけのこもく)

樹木は元口より末口に向かって径が細くなるため、樹心に平行な板目の裁断面
には筍状に山形の杢が現れますスギ
やケヤキ
など、春材と夏材の差がはっきり
とした肌目のものが、分かりやすくて美しいとされます。